行政書士試験の憲法で重要な判例の一つに、「八幡製鉄献金事件」があります。
この事件は、会社による政治献金の適法性や、それに伴う法人の人権などが争われた画期的な裁判です。
行政書士試験の学習において、この判例をしっかりと理解することは、法的な思考力を養う上で非常に有益です。
憲法の人権規定は法人にも適用されるか?
→憲法の人権規定は、権利の性質上可能な限り、法人にも適用されます。ただし、選挙権や生存権など、自然人のみに結びつく権利は除かれます。
株式会社の政治献金は許されるか?
→株式会社も、性質上可能な限り憲法上の人権が保障され、自然人たる国民と同様に政治的行為をする自由を有するため、政治献金も原則として許されます
事件の背景
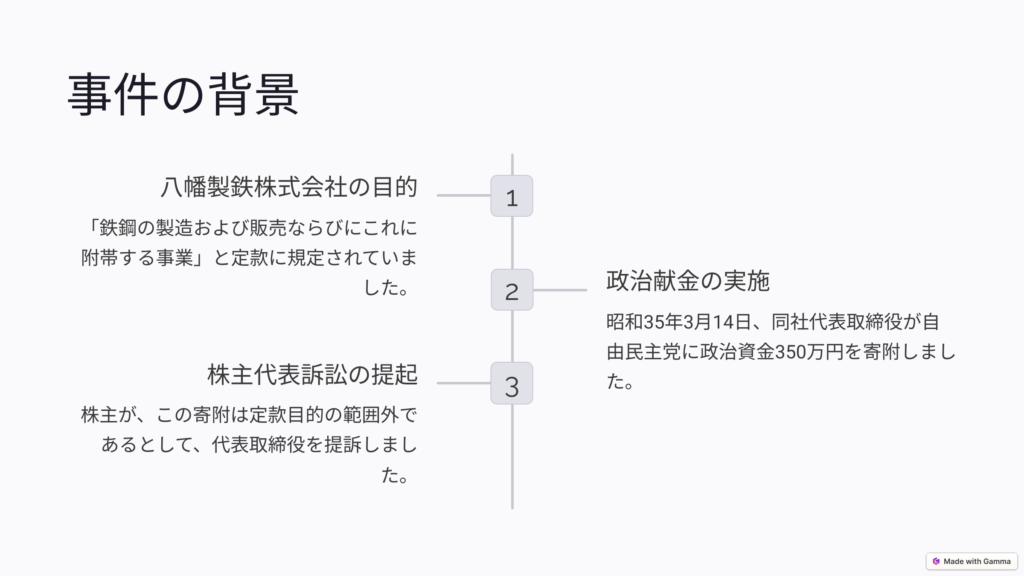
八幡製鉄株式会社は、定款で「鉄鋼の製造および販売ならびにこれに附帯する事業」を目的とする会社でした。
その代表取締役は、昭和35年3月14日、会社を代表して自由民主党に政治資金350万円を寄附しました。
これに対し、八幡製鉄株式会社の株主が、この寄附は会社の定款に定められた目的の範囲外であり、会社にはそのような寄附をする権利能力がないとして、代表取締役らの責任を追及する株主代表訴訟を提起しました。
個々の私法人の組織・活動について定めた根本規則
主要な争点
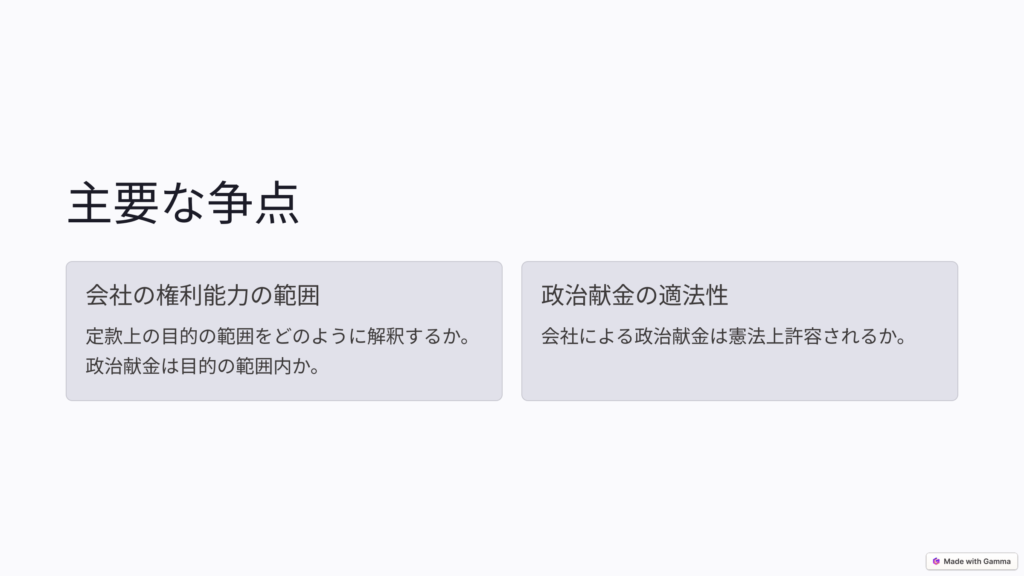
この裁判では、主に以下の点が争われました。
- 会社の権利能力の範囲: 定款に定められた目的の範囲内の行為とは、具体的にどこまでを指すのか。政治献金は、会社の目的の範囲内の行為と言えるのか。
- 会社による政治献金の適法性: 会社が政党に政治資金を寄附することは、憲法に反するのではないか。特に、自然人にのみ参政権が認められている憲法の趣旨に反しないか。
(権利義務の主体である)生きている自然の人。
最高裁判所の判断
最高裁判所は、以下の理由から上告を棄却し、会社による政治献金は一定の範囲内で適法であるとの判断を示しました。
会社の権利能力について
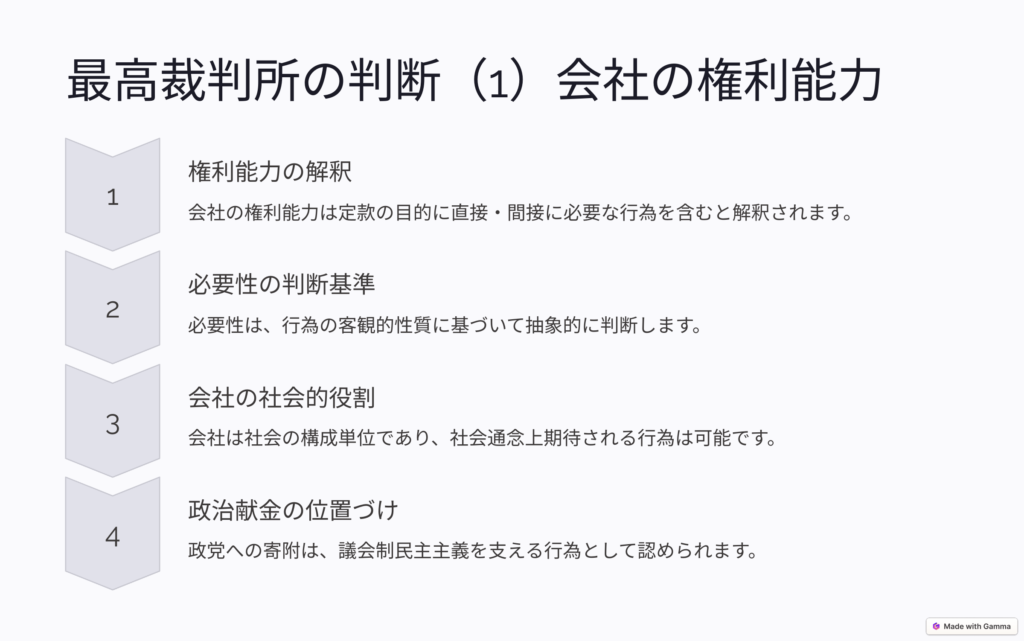
最高裁は、会社の権利能力は定款に明示された目的自体に限らず、その目的を遂行する上で直接または間接に必要な行為を全て含むと解釈するのが相当であるとしました。そして、必要性の判断は、行為が目的遂行上現実に必要であったかどうかではなく、行為の客観的な性質に即し、抽象的に判断されるべきであるとしました。
その上で、会社は営利事業を営むことを本来の目的とする一方で、社会の一構成単位としての役割も担っており、社会通念上、会社に期待ないし要請される行為を行うことは、会社の当然なしうるところであるとしました。
政治資金の寄附も、政党が議会制民主主義を支える不可欠の要素であり、国民の政治意思を形成する上で重要な媒体であることから、その健全な発展に協力することは、会社に対しても社会的存在としての当然の行為として期待されるとしました。
したがって、会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められる限りにおいては、会社の定款所定の目的の範囲内の行為であるとしました。
会社による政治献金の適法性について
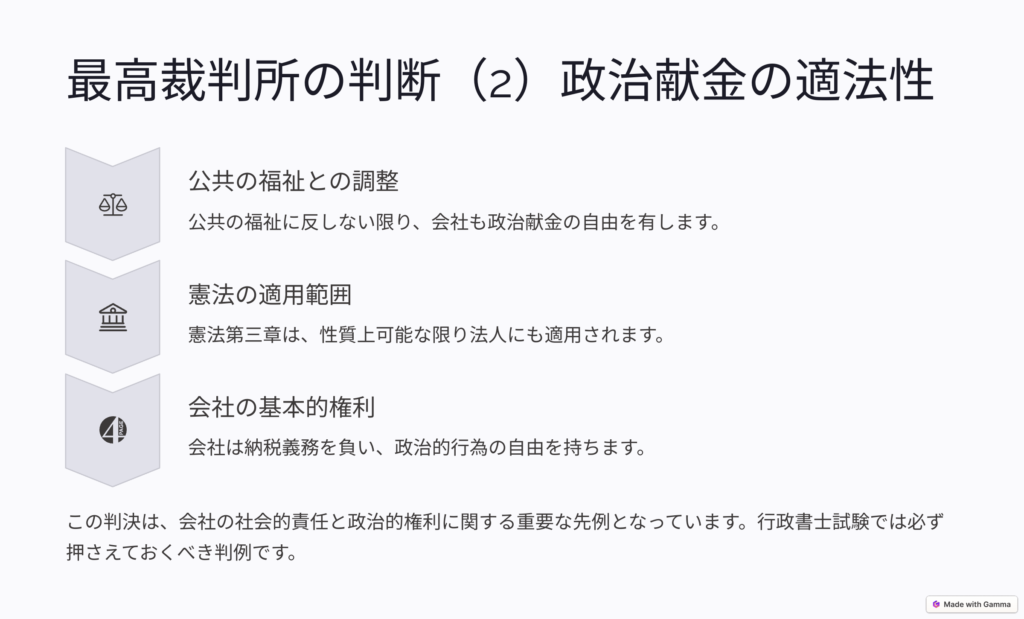
最高裁は、会社が納税の義務を負い、自然人たる国民と同様に国や地方公共団体の施策に対し意見表明などの政治的行為をする自由を有するとしました。
憲法第三章の国民の権利および義務の各条項は、性質上可能な限り内国の法人にも適用されるべきであり、政治資金の寄附もその自由の一環であるとしました。
会社による政治資金の寄附が政治の動向に影響を与えることがあったとしても、自然人たる国民による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請はないとしました。公共の福祉に反しない限り、会社も政治資金の寄附の自由を有すると結論付けました。
行政書士試験との関連性
八幡製鉄献金事件は、行政書士試験において以下の点で重要な示唆を与えます。
- 基本的人権の享有主体: 憲法で学習する基本的人権の享有主体について、法人にも一定の権利が認められることを示す重要な判例です。
- 政治活動の自由: 会社も一定の範囲で政治活動の自由を有するという判断は、表現の自由や政治献金の自由といった論点と関連します。ただし、外国法人の政治活動については、マクリーン事件などの判例も参照し、在留資格との関係で制限を受ける場合があることも理解しておく必要があります。
憲法の人権規定は法人にも適用されるか?
→憲法の人権規定は、権利の性質上可能な限り、法人にも適用されます。ただし、選挙権や生存権など、自然人のみに結びつく権利は除かれます。
株式会社の政治献金は許されるか?
→株式会社も、性質上可能な限り憲法上の人権が保障され、自然人たる国民と同様に政治的行為をする自由を有するため、政治献金も原則として許されます
一方、強制加入の南九州税理士会事件では反対の判決がでました。
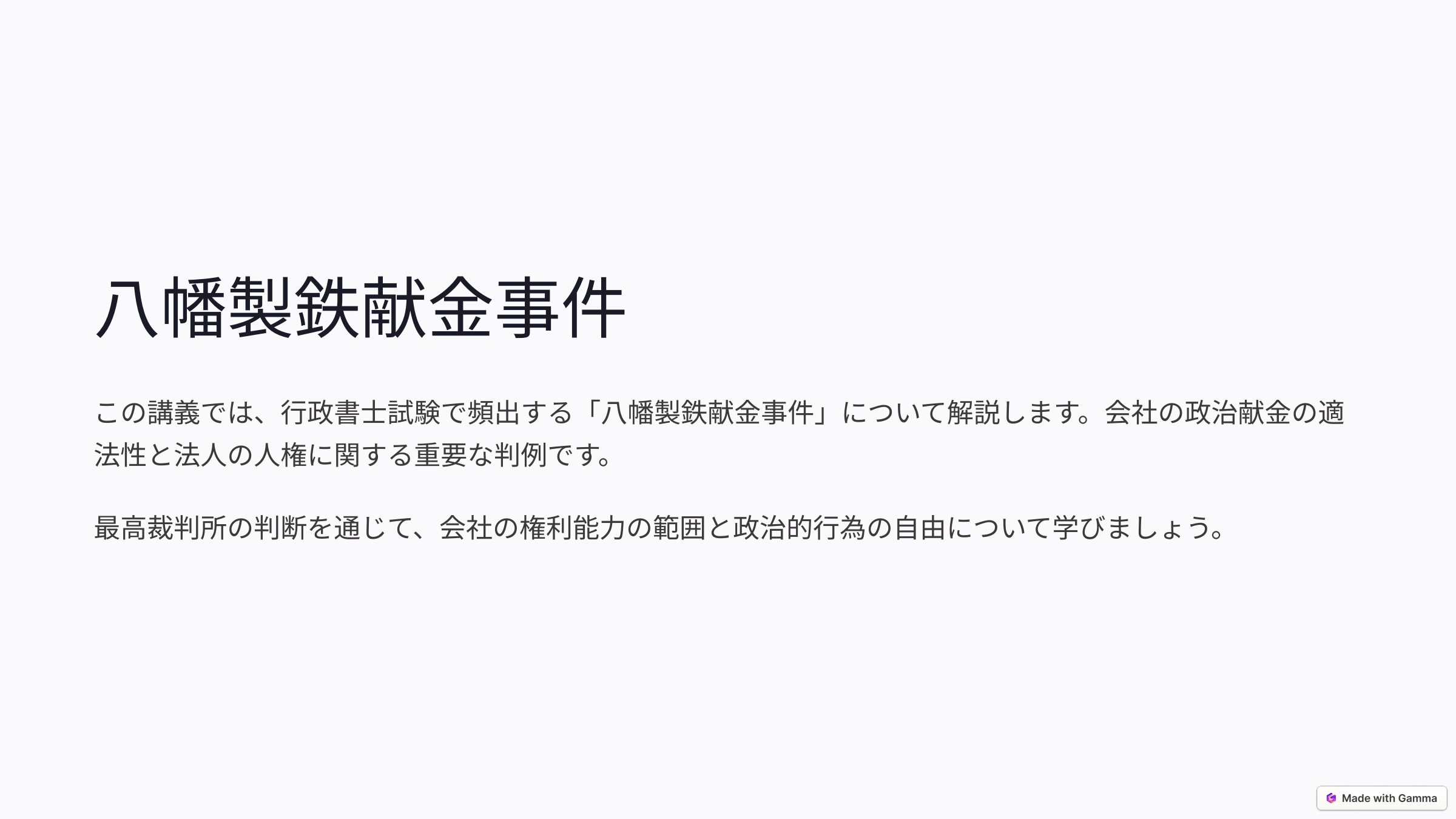





コメント