皆さん、こんにちは。行政書士試験の学習、お疲れ様です。 今回は、人権分野でよく問われる重要判例の一つである「指紋押捺拒否事件」(最高裁判所平成7年12月15日大法廷判決)について、試験対策として押さえておくべきポイントを中心に解説します。
事件の概要
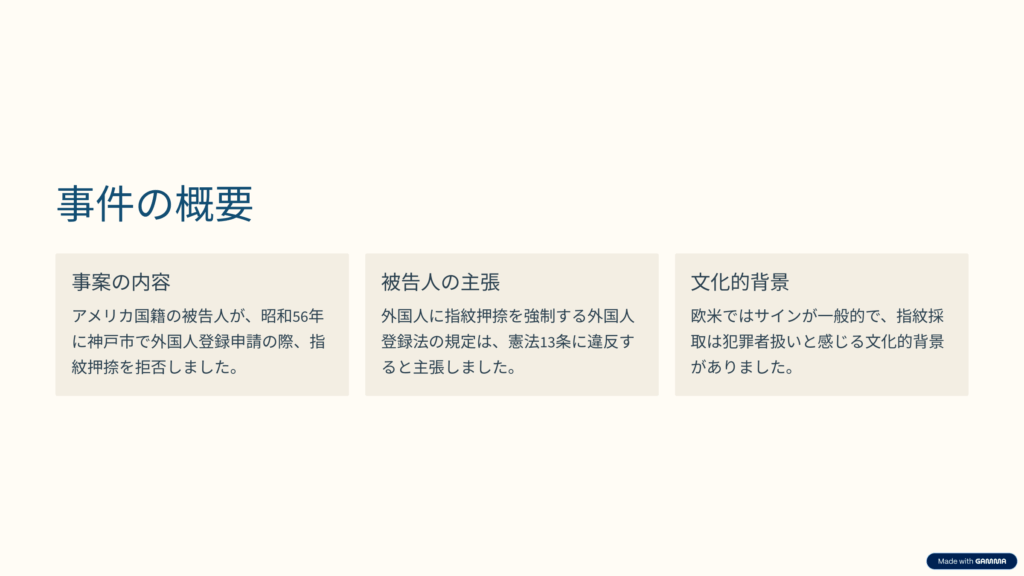
この事件は、当時アメリカ合衆国籍を有しハワイに在住していた被告人が、昭和56年11月9日に来日し居住していた神戸市で、新規の外国人登録の申請をした際に、外国人登録原票や登録証明書、指紋原紙に指紋の押捺をしなかったことから、当時の外国人登録法に違反するとして起訴された事案です。 被告人は、外国人に対して指紋押捺を強制する外国人登録法の規定は、憲法13条に違反すると主張して争いました。
争点
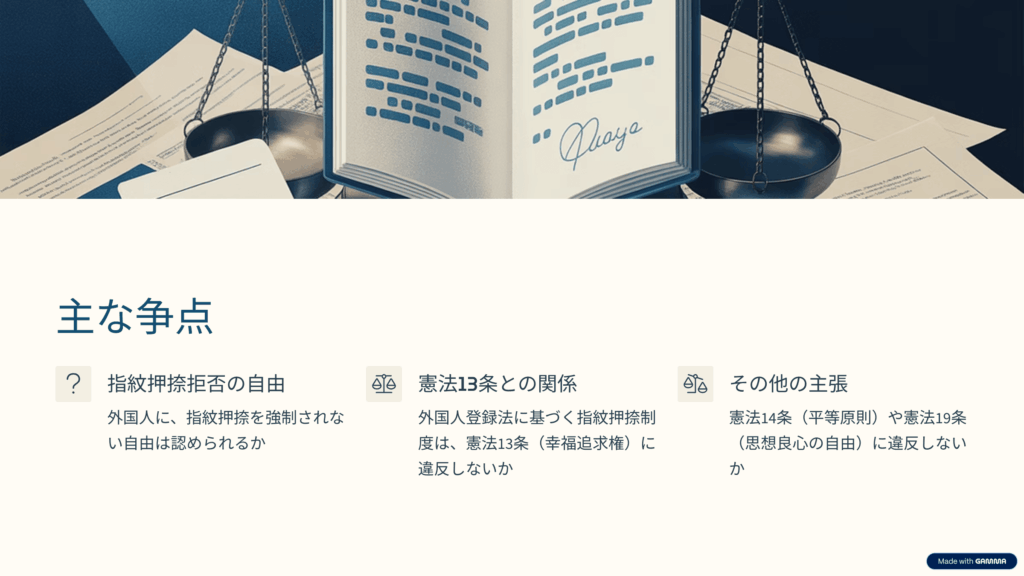
この事件の主な争点は以下の点でした。
- 外国人に、指紋押捺を強制されない自由は認められるか。
- 当時の外国人登録法に基づく指紋押捺制度は、憲法13条に違反しないか。
被告はその他、外国人に対する指紋押捺制度が、日本人と異なる扱いをする点で憲法14条(平等原則)に違反する、または思想良心の自由(憲法19条)を害する、とも主張しました。
最高裁判所の判断
最高裁判所は、これらの主張に対して以下のように判断しました。
憲法13条(幸福追求権)について
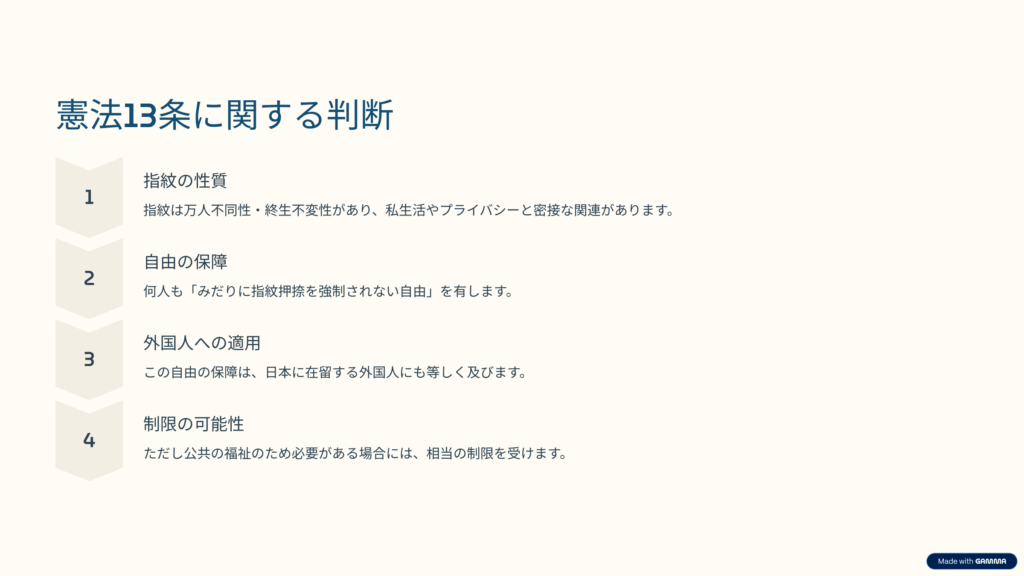
- 指紋は、指先の紋様であり、それ自体で個人の内心に関する情報となるものではありません。しかし、指紋には万人不同性・終生不変性という性質があり、採取された指紋の利用方法次第では、個人の私生活やプライバシーが侵害される危険性があります。このような意味で、指紋の押捺制度は個人の私生活上の自由と密接な関連を持つと考えられます。
- 憲法13条は、国民の私生活上の自由が国家権力に対して保護されるべきことを規定しています。したがって、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押捺を強制されない自由を有すると解されます。
- そして、国家機関が正当な理由もなく指紋の押捺を強制することは、憲法13条の趣旨に反して許されません。「みだりに」とは、「これといった理由もなく」という意味です。
- この「みだりに指紋押捺を強制されない自由」の保障は、我が国に在留する外国人にも等しく及ぶと解されます。
- ただし、この自由も、国家権力の行使に対して無制限に保護されるものではなく、公共の福祉のため必要がある場合には相当の制限を受けることは、憲法13条の定めるところです。
- 当時の外国人登録法が定める在留外国人についての指紋押捺制度は、「本邦に在留する外国人の登録を実施することによって外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もって在留外国人の公正な管理に資する」という目的で制定されたものです。これは、戸籍制度のない外国人について人物特定を確実に行うための制度でした。
- その立法目的には十分な合理性があり、かつ必要性も肯定できると判断されました。
- また、当時の制度内容(本件当時)は、押捺義務が3年に一度で、対象指紋も一指のみ、強制も罰則による間接強制にとどまるものでした。これは、精神的・肉体的に過度の苦痛を伴うものとはいえず、方法としても一般的に許容される限度を超えない相当なものであったと認められました。
- したがって、このような指紋押捺制度を定めた外国人登録法の規定は、憲法13条に違反するものではない、と結論付けられました。最高裁は、被告人の上告を棄却しました。
憲法14条(平等原則)について
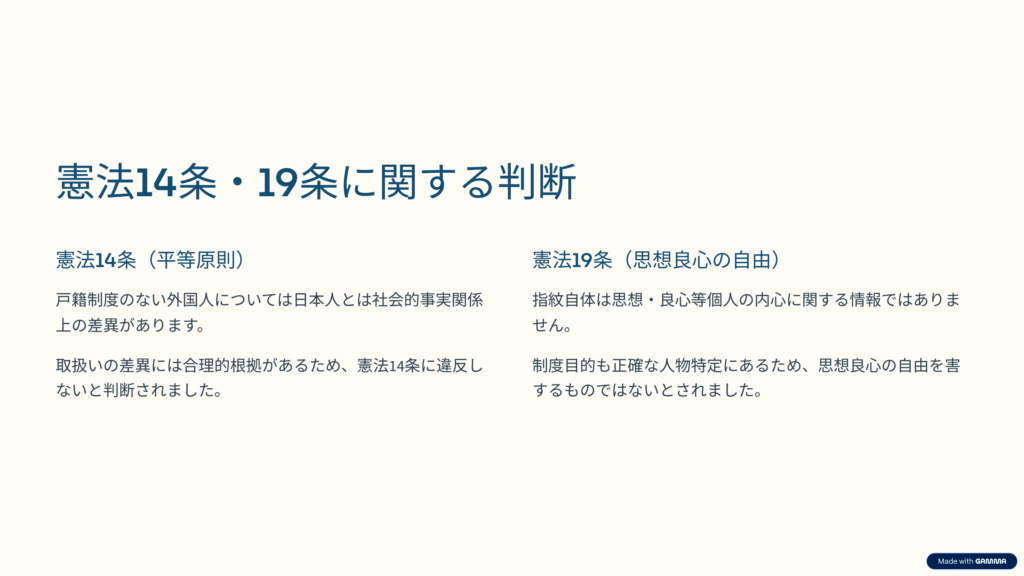
- 外国人に対する指紋押捺制度が、日本人と同一の取扱いをしない点で憲法14条に違反するという主張については、在留外国人を対象とする指紋押捺制度には、上記のような目的、必要性、相当性が認められ、戸籍制度のない外国人については日本人とは社会的事実関係上の差異があることから、その取扱いの差異には合理的根拠があるとして、憲法14条に違反しないと判断されました。
憲法19条(思想良心の自由)について
- 指紋押捺制度が外国人の思想、良心の自由を害するという主張については、指紋自体が思想、良心等個人の内心に関する情報となるものではなく、制度目的も在留外国人の公正な管理に資するための正確な人物特定にあることから、思想良心の自由を害するものとは認められないとして退けられました。
試験対策として押さえておくべきポイント
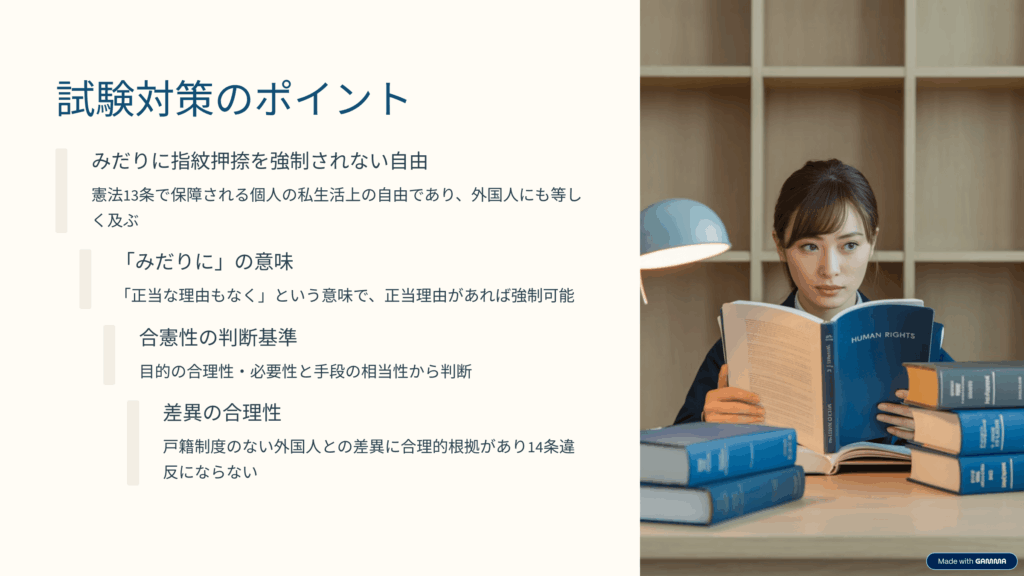
- 何人もみだりに指紋押捺を強制されない自由は、個人の私生活上の自由として憲法13条で保障されること、そしてこの自由は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶこと。
- 「みだりに」とは「正当な理由もなく」という意味であり、正当な理由があれば指紋押捺を強制することは許されること。
- 当時の外国人登録法に基づく指紋押捺制度は、目的(在留外国人の公正な管理のための人物特定)に合理性・必要性があり、方法(3年に一度、一指、間接強制など)も相当であった ため、公共の福祉による憲法13条の制限として合憲と判断されたこと。
- 憲法14条違反については、戸籍制度のない外国人との差異に合理的根拠があるとして合憲と判断されたこと。
まとめ
指紋押捺拒否事件は、憲法13条が保障するプライバシー権としての側面と、公共の福祉による権利の制限、そして制度の目的・手段の合理性・相当性が問われた重要な判例です。最高裁は、「みだりに指紋押捺を強制されない自由」は外国人も含めて保障されるとしつつも、当時の外国人登録制度については、目的・手段の点から合理性・必要性・相当性があるため合憲であると判断しました。この判例の結論に至る論理の流れをしっかり理解しておくことが、試験対策には不可欠です。
この解説が、皆さんの学習の一助となれば幸いです。頑張ってください!
参考リンク
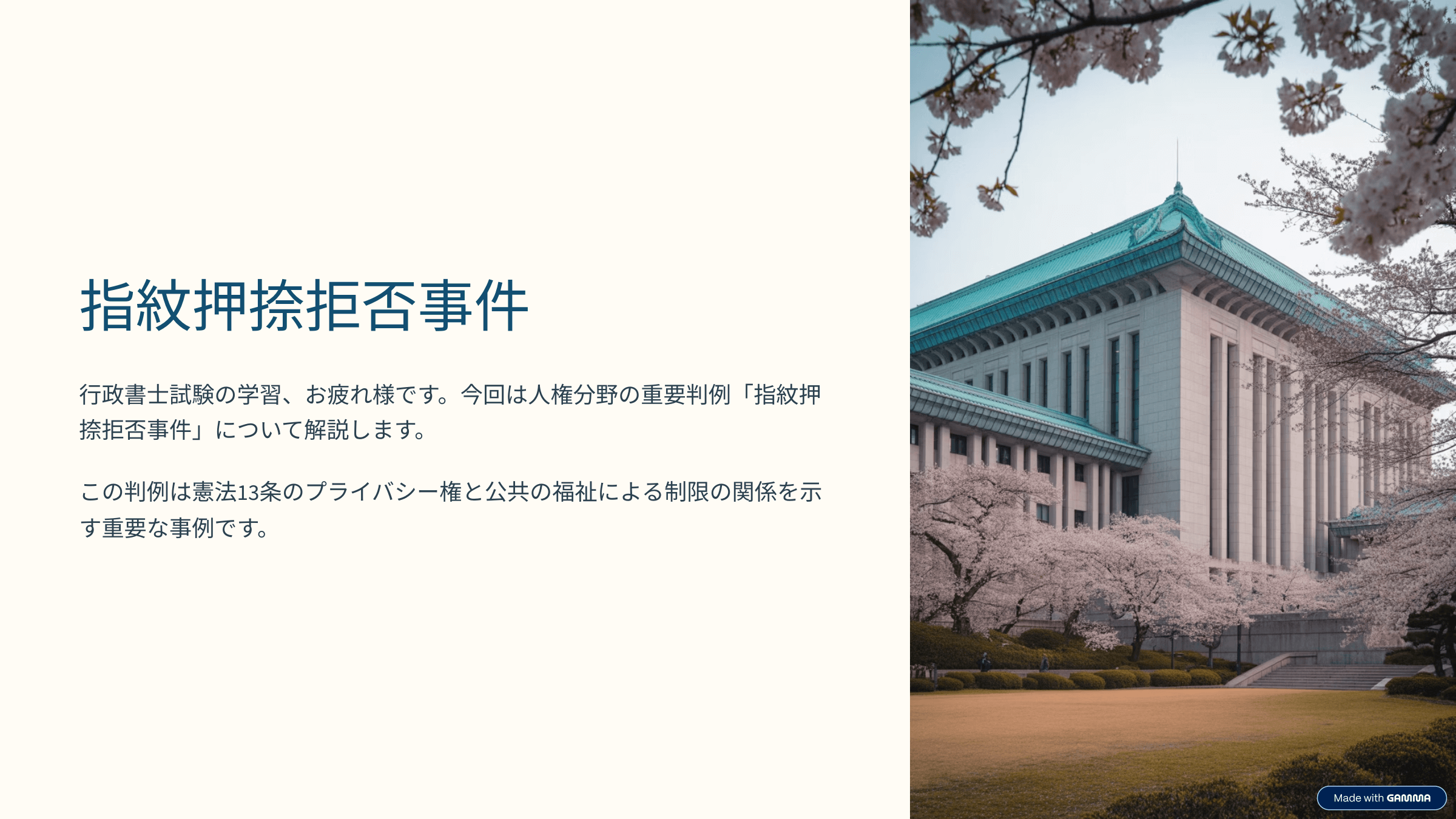
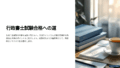
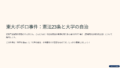
コメント